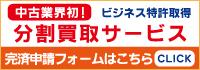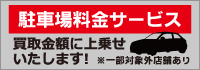桜の季節に気温が下がって長持ちするのはいいのですが雨が続くと撮影が進まずフラストレーションがたまるelmarです。
現代は日常の記録はスマートフォンで行うことがほとんどですが古めのデジカメやフィルムカメラで印象的な写真を撮る方もいらっしゃるようです。
それも比較的、若い方々が多いようでelmarのようなおじさんが昔懐かしさで使うのとは視点が違うのかも知れません。
今回は手持ちのちょっと古いデジカメを使って印象的な、いわゆるエモい写真にチャレンジしてみます。
メインで使うデジカメはこちらです。
RICOH GXR+S10 24-72mm F2.5-4.4 VC
このカメラの発売は2009年ですからもう15年以上前のカメラですね。
GXRはユニット交換式のデジタルカメラでライカMマウントやGRレンズを搭載したユニットなどが用意され非常に意欲的な製品でした。
ラインナップされていたユニットは下記の通り。
RICOH LENS S10 24-72mm F2.5-4.4VC
RICOH LENS P10 28-300mm F3.5-5.6
RICOH LENS A16 24-85mm F3.5-5.5
これらのうちA12は1200万画素クラスAPS-CサイズCMOSセンサー搭載、A16は1600万画素APS-CサイズローパスレスCMOSセンサー搭載で高画質を狙ったユニットだったようです。
ボディはほぼ「板」とグリップといった体裁でユニット側にCCDやレンズを組み込んだユニットを取り替える面白いカメラでした。
過去に当ブログでも何回か取り上げています。
2011年頃の今回と同じくS10ユニットのレビュー記事です。
こちらはA12 LENS MOUNT UNIT導入時に公開した記事で各種Mマウントレンズを試しています。
現在、elmarの手元に残っているのはS10 24-72mm F2.5-4.4 VCユニットで撮像素子は1000万画素 1/1.7型CCDですから現代のスマートフォンには到底、敵わないスペックです。
こういった諸元以上にオートフォーカス(以下、AFと表記します)の遅さやダイナミックレンジの狭さなどHDRの写真が一般的になっている現代では快適に使う事は困難かもしれません。
elmarはマニュアルフォーカス(以下、MFと表記します)のレンズやフィルムカメラを多用しているので気になりませんがミラーレス一眼と標準レンズしか使った事のない人からすればその不便さに些かイライラさせられる事でしょう。
おそらくメーカーもこの点は認識していたらしくフルプレススナップ機構が搭載されていました。
これは当時のRICOH GR シリーズにも同様に搭載されていてシャッターを半押しせずに押し切ると指定の距離に固定されAF動作を行わないためタイムラグを最小限にできる機構です。
例えば設定撮影距離を2mに設定し絞りをF8くらいで設定しておけば被写界深度が深くなり近距離から遠距離までピントがあうパンフォーカスで撮影できシャッターチャンスを逃しません。
それでも電源オンから撮影可能になるまでに少し待たされてしまいますが。。。
さて、そんなわけで外装のクリーニングとバッテリー充電をして撮影に出かけましょう!
CCDかCMOSかは当時、よく議論されたテーマでしたが結局は画像生成エンジンによる所が大きいので素子そのものはどちらでもよいような気がします。
RAW現像する場合はCCDの方が抜けがよく仕上がる傾向があるかもしれません。
このカットのように緑や青空といった原色系は得意とするようです。
GXRにはシーンセレクトモードがあり様々なエフェクトをかける事ができます。
そのうちの一つ「ソフトフォーカス」を使用します。
春の光が滲んだように描写されてなんだか夢の中のような描写です。
購入当時から愛用していた「ハイコントラスト白黒」モードで撮影してみます。
ハイコントラスト白黒モードは日常をドラマチックに描写できる面白いモードです。
さらにISO感度1600に設定すると1000万画素の低画質(?)と相まって粒子感、ノイズ感のあるザラっとした描写になります。
ザラっとした質感が印象を強くし、ギラギラとした写真になります。
このようにGXRは面白い描写が愉しめるカメラです。
GXRカメラユニットなども稀に中古市場にも出てきますので気になるかたは気長に探してみてください。
続いてご紹介するのはこちら!
2009年10月の発売のレンズ一体型デジタルカメラです。
当ブログにも過去にちょっとだけ登場させています。
独自のAPS-CサイズFoveonX3 COMSセンサー搭載で通常のベイヤー配列CMOSとは一線を画す高画質をねらったモデルです。
1460万画素ですがFoveonX3センサーのため実際はさらに高画質な結果が得られます。
搭載されるレンズは16.6mmF4でフルサイズ換算で28mmに相当します。
このセンサーを搭載したカメラはその後、Merill、Quatroと代を重ねていきますが現在はラインナップされていません。
SIGMAでの開発は継続しているようなので気長に待っています。
カメラの機能としては変わった点はありませんがMFダイヤルが親指の当たる位置にあるのが特徴的ですね。
このカメラはセンサーの性能は素晴らしいのですがインターフェイスやホワイトバランス、AF性能は開発途上といったところで動作は非常に緩慢です。
本機のAFはコントラスト検出式で現代の位相差検出式AFと比べると速度、精度ともに
遅い上にピントを外す事も多く使用するには寛大な心が必要かも。
作例は全てJPEG撮って出しで補正なしです。
ようやく訪れた晴天下での桜撮影の機会。
手前の菜の花とともに色の分離がよくスッキリしています。
桜のクローズアップ。
背景の青空が飛ばない程度に露出補正を入れています。
このカメラはセンサーの性能は素晴らしいのですがインターフェイスやホワイトバランス、AF性能は開発途上といったところで動作は非常に緩慢です。
特にAF性能は遅い上にピントを外す事も多く使用するには寛大な心が必要かも。
絞り開放F4での撮影。
ボケ味はごく自然ですがやや周辺光量落ちが見られますがピントの合ったところの解像度は素晴らしいものがあります。
再開発が進む新宿駅周辺。
F8以上に絞り込んで撮影すると隅々まで解像してセンサーの高精細さと相まってFoveonらしい描写となりました。
無機質なコンクリートやガラスといったものの質感がよく切れ味の良い刃物を使っているような感覚があります。
標準搭載されているB/Wモードで撮影。
Foveonによるモノクロは解像度が高くトーンもよく出ますのでモノクロ専用機として使用しても面白いでしょう。
同じ場所でカラー撮影していますが青空の色味がもう一つなのでRAW現像で追い込みたくなります。
某アニメ(漫画)の「ピーキー過ぎてお前にゃ無理だよ」ってセリフが聞こえてきそうです。
注意点としてはバッテリーが入手できない場合があるのと記録メディアがSDHCまでの対応であり最大容量が32GBである点でしょうか。
今回、稼働させるにあたってelmarの場合、メディアのほとんどが64GB以上のSDXC規格を常用しており、32GB以下のメディアを家中を捜索する羽目になりました(笑)
さていかがだったでしょうか。
オールドデジカメでの撮影はスマートフォンでサクサク撮って共有できる快適さはないものの一味違った自分だけの一枚を残す事もできます。
オールドレンズやフィルムカメラにもいえる事ですが大切なのは当時の技術者が最大限の努力をして世に送り出した製品である事です。
演算やAIで手軽にソレっぽい加工が出来てしまう現代とは違い、ある意味で本物であるともいえるでしょう。
技術の進歩は素晴らしいですが感性や現場での空気はその場所でなければ残せませんし感じられません。
お手元に使っていないカメラがあれば動かしてあげてください。
もちろん、ご不要の場合はじゃんぱらで買取いたしますのでご相談ください。
ご利用お待ち申し上げております。
以上、elmarがお送りしました。